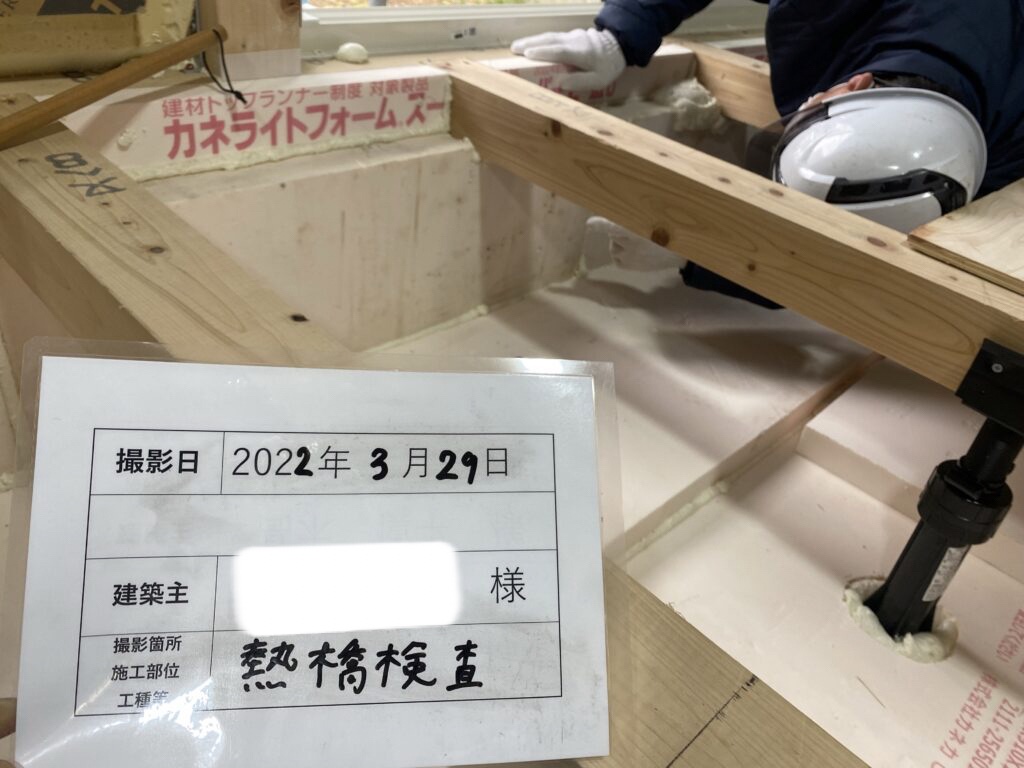皆さんこんにちは!
凰建設株式会社 工事部の山下です。
本日は、これから始まる工事の打ち合わせに専務とお伺いしてきたのですが、なるほど!と感じることが多くありました。
断熱改修工事は外から付加断熱にするパターンと、室内から取り付ける方法があります。
室内から施工する場合は床や壁、天井を解体して施工するのですが今回は断熱処理だけだから、構造の補強はいいかな。防蟻処理はいいかな。と判断してしまうのではなく今後、10年後も地震に強く防蟻効果もあった方が良いですよね。
なので、工事のご提案する時も今回の工事を第一に考えるのですが、将来的にも考えてみたいと思いました。
本日は給気と排気についてご紹介致します。
給気と排気、字のごとく空気を取り入れる所と空気を排出する所があります。
高気密のお住まいで、給気と排気のバランスが悪い空間ですと、玄関のドアが重い事や開きにくいなどといった事態が起こってしまいます。
レンジフードでも、通常は排気だけのレンジフードが採用されています。しかし、高性能住宅の高気密高断熱のお住まいでレンジフードをつけると室内が『負圧』になってしまいます。
そうなると、玄関ドアなどが開きにくくなる。各部屋に設けてある給気口(排気も)から空気がレンジフードに流れていく現象が起こってしまいます。
また、夏に冷房をつけても全然涼しくない・冬に暖房をつけても部屋が暖まらない事が起こってしまいます。(熱損失)
このようなことが起こらないように、同時給排気ができるレンジフードを採用し室内の気圧を安定させる事。また計画換気が正確に行えることが大切だと思います。
下記の写真を見ていただけるとダクトが2本あるのが分かると思います。これはレンジフードの給気と排気のダクトに断熱が巻いてあります。
なぜ巻いてあるのかというと、ダクトを通る外の空気と室内の空気により夏は内側に冬には外側に結露が発生してしまいます。このような事が起こらないようにダクトを断熱を巻いています!

換気は、給気と排気があることで空気の入れ替えができます。
もし換気をしないと、どうなるのか?
室内の二酸化炭素、ホコリ、湿気などが溜まった状態になります。そうなると、シックハウス症候群を引き起こし健康被害にもなってしまう事が…。
症状として、目のかゆみ鼻水などアレルギー症状や酷くなってしまうと”めまい”や嘔吐を引き起こしてしまうことがあります。
このような事が起こらないよう”給気と排気”を設けて空気の入れ替えが必要不可欠だと言うことですね。
※給気口、排気口に設けてあるフィルターはこまめに清掃をお願い致します。
本日もブログをご覧下さいましてありがとうございます!今後ともよろしくお願い致します。